HOUSE VISION研究会報告|日本
第2回「リノベーションを考える」2011年3月28日
第1回研究会の4日後、東日本大震災が起こった。第2回研究会は、世話人である原研哉の次のような挨拶から始まった。「日本は今後しばらく、被災地の復興に向けて力を注ぐことになるでしょう。同時に、その復興を通して新しい日本のカタチが生まれてくる可能性もあります。原発事故による電源不足は、日米がスマートグリッド構想を次代のエネルギー社会の目標と据えた矢先に日本が直面した問題であり、電気自動車やプラグインハイブリッド車の販売などと合わせて計画が一気に進むことが考えられる。さらに言えば、家の形を変えていくようなイノベーティブな動きも出てくるだろう。同時に日本人がエネルギーに対する新しい意識を持ち、思想的にエネルギー先進国へと切り替わる節目にもなるはずです。復興の槌音が聞こえてくるまで態度を保留にするのではなく、それも踏まえた上で、日本の住まいのカタチを捉え直していくHOUSE VISIONの活動は粛々と進めていきたいと考えています」
「リノベーションを考える」にあたって|原研哉
「家」が日本の産業の未来にとって大きな交差点となる可能性が見えている。まず、人口が減少傾向にあり日本は縮態化していくこと。エネルギー問題が大きな曲がり角に差し掛かっていることなどから、日本の産業技術は工業製品をつくるだけでなく、機能が「家化」、すなわち環境化していくことにシフトしていくだろう。同時に20世紀型のビジネスモデルと言える、右肩上がりの土地開発・販売ビジネスの仕組みは終りを告げ、そうした土地ビジネスでは邪魔者になっていた「建築」が浮上してくる。これからの日本に生み出される「家」への新しい創造性は、新たな価値観を育み、新しい日本の産業となり、内需拡大と同時に中国やアジア諸国にとっても魅力的な輸出商材になっていくのではないだろうか。
日本は高齢社会に突入しているが、老齢化をネガティブに考えるのではなく、こうした世代のために経験を積み、経済的にも豊かで、成熟した大人のプリンシプルを発揮できる市場をつくる。そうしたマーケティングを日本が世界に先駆けて実現するなら、今後の世界のマーティングを日本が先導していくことになるだろう。しかし未だその良質なリファレンスがない。HOUSE VISIONでは、こうした「家」の可能性を具体的なビジョンとして、理想的なカタチを社会に流通させていくことを考えている。これはモノづくりのプロジェクトではなく、情報と覚醒のプロジェクトである。
多く人々が海外での日本が持つ文化的なポテンシャルに気付き始めている。経済的に発展している中国やアジアの諸国では、家に対する所有欲はあるが、住まいのディティールに対する欲望は高くない。一方、日本人は生活に対する希求の水準が非常に高い。しかしその豊かな土壌にどんな木を植えて、どんな実を収穫するか。私たちはその「収穫」までを考えてみたい。

- 馬場正尊 Masataka Baba
建築家・Open A代表・東北芸術工科大学准教授 - 1968年佐賀県生まれ。1994年早稲田大学大学院建築学科修了。博報堂、早稲田大学博士課程、雑誌『A』編集長を経て、2002年Open A を設立。都市の空地を発見するサイト「東京R不動産」を運営。東京のイーストサイド、日本橋や神田の空きビルを時限的にギャラリーにするイベント、CET(Central East Tokyo)のディレクターなども務め、建築設計を基軸にしながら、メディアや不動産などを横断しながら活動している。元新聞工場をクリエイターのオフィス、スタジオ、カフェ等の複合施設に改修した「TABLOID(2010,グッドデザイン賞)」、無印良品+リビタによるリノベーションプロジェクトCase01(2008),Case02(2009))など。著書に「未来の住宅 カーボンニュートラルハウスの教科書」(バジリコ)、「都市をリノベーション」(NTT出版)など。
リノベーションは
特殊解から一般解、
そして普通のことになる
建築に関わる私たちの耳に「リノベーション」という単語が届き始めたのは2001~2002年だったと思う。この頃に日本にリノベーション産業の萌芽が起こる(リノベーションは日本独自の表現で海外では一般的ではなく、コンバージョンという表現が使われている)。それから約10年。私はそれと並走し、リノベーションの仕事に携わることになった。まずこの10年ほどの動きを、自分の仕事を含めて紹介し、それがこの研究会の序章的なものになれば良いと思っている。
私はOpen-A(http://www.open-a.co.jp)という設計事務所を主宰し、リノベーションだけでなく戸建て住宅の設計も行っている。私にはもはや戸建住宅とリノベーションの間の境界はない。日本ではリノベーションはサブカルチャーとして始まり、今からまさに産業になろうとしている。いわば「文化として生まれ産業として育つ」である。
私が普通の建築家と決定的に違うと思うのはキャリアである。私は建築を学んだ後に広告代理店でメディアの開発に携わった。そのためプロジェクトを動かす時に、どうメディアを使うかについて意識的である。例えば、私は「東京R不動産」というちょっと変わったウェブサイトを運営している。東京のちょっと面白い空き物件、リノベーションとしての空き物件、その可能性がある物件ばかりを集めたウェブサイトだ。メディアであると同時に、実際に不動産の仲介ができるツールとしても機能している。このメディアの存在がリノベーションのアクセルになったと思う。
アメリカの事例から

私がリノベーションに興味を持ったきっかけは2002年。不良債権化した空き物件を抱えたある金融機関から、物件をバリューアップして賃貸や売却をしたいと相談を受けた。最初はインテリアの仕事だと思ったのだが、よく考えると産業構造的な問題が見えてきた。これは市場になると気づいたのが10年前のことだ。そこでアメリカに取材旅行に出かけ、さまざまな事例を見学した。それをいくつか紹介したい。
まずロサンゼルスから。LAの中華街「Chung-king Road」は捨て去られたように寂れた街区だったが、住民自ら建物内をギャラリーに改築することで街が見事に再生していた。次の事例は古書店。古本屋を古本屋のままカフェにしている。それがすごく流行っていた。聞いていくと古書店という文化を継承しているから流行っているのだとわかってくる。リノベーションはハードだけではなく、いかに歴史や文化の文脈を継承するかが重要であるかを感じた。ノースセントラルアヴェニューの「THE GEFFEN CONTEMPORARY AT MOCA」は元百貨店。廃墟になっていたデパートを子どもたちのワークショップのために再生した施設だ。再生した建物だから、子どもたちは汚し放題。リノベーションはハードだけで見てはいけないのだと思った。次はシカゴ。シカゴは物流の変革のため中心市街地の倉庫が空き物件だらけになっていた。シカゴでFitzGerald Associates Architectsによる、倉庫を住宅にコンバージョンした事例を見た時は、住宅はコレで十分だと思った。仕上げも壁も建具もいらない。シカゴではコンバージョンは、新築、中古と並び、住宅取得のための選択肢の一つに過ぎない。しかもコンバージョンは新築を入手するより高価な場合がある。それは、天井が高く空間性が豊かだったり、建築の歴史を引き継ぐことができるからであるという。それを聞いてなるほどと思った。
東京R不動産
こうした事例を見て私は、文化として定着して、それが産業になっていくのだと感じていた。では日本のリノベーションとは何か。まず何か事例をつくろうと小さなところから始めた。神田の裏通りに家賃10万円の駐車場があり、これを借りて自分でリノベーションした。今は私たちの事務所の一部になっている。とりあえず白く塗っただけだが、最初の一歩を踏み出したわけだ。このプロセスの中で「東京R不動産」(http://www.realtokyoestate.co.jp/)というウェブサイトを思いついた。
この物件は借りる際に非常に苦労した。改装しても構わない物件を探して不動産仲介業者を訪ねても、現状復帰義務を盾に了解が得られず、物件探しは困難を極めた。だが、現実には魅力的な空き物件はたくさんある。それをブログで紹介すると、「借りられないか」という問い合わせがくる。渋谷区の「ビラ・モデルナ」は坂倉準三が手掛けた集合住宅だが、街の不動産仲介業者では単なる築40年のボロ物件として扱われている。しかし私たちから見ると歴史的建造物。そういう紹介をすると一気に人気物件になる。要は伝え方なのだと感じた。ここにはニーズがあると考え、スタートしたのが「東京R不動産」だった。現在は月間ページビューは300万、会員2万数千人の大きなウェブサイトになっている。不動産、建築デザイン、メディアとバラバラだった三者のノウハウを融合することで成立し得たウェブサイトだと思う。
OSとアプリケーション
こうしたメディアが基軸になり、自分でもリノベーションの仕事に着手し始めた。古いオフィスビルや倉庫のリノベーションを手掛けたものの、これらはまだ特殊解だと見ていたが、普通の木造住宅のリノベーションの依頼が来た頃から、リノベーションはかなり一般化してきたのではないかと感じるようになった。さらに無印良品からリノベーションを請けた時に、やはり一般化しているという実感を得た。普通の集合住宅のスケルトンを使い、壁と棚を手がかりに暮らしの変化に対応できるリノベーションをいくつか提案した。新築に対するアンチテーゼで、現在の新築集合住宅は一度買ってしまうと、子どもが増えようが離婚しようが変えられない。私が提案したリノベーションは家族の変化に合わせて伸縮自在になる設計だ。新築よりもリノベーションのほうが自由ではないかと思う。
このプロジェクトでは「OSとアプリケーション」という考え方を応用している。まず空間のOSを設定する。簡素、簡潔な住まいであり、変化に柔軟で、永く住み続けられる住まいでOSをつくる。コントロールしたスケルトンというイメージ。そこに物件、生活、家族に合わせたアプリケーションを用意する空間の展開方法を考えた。最適解は住まい手がつくりあげるシステムをつくる。
ここまで説明したことは、リノベーションが特殊解から一般解へと移行するプロセスだが、今後はさらにユーザー自身の手でリノベーションを拡大できないかと考えた。そこで「東京R不動産」にTOOLBOXというウェブサイトをスタートさせてみた。リノベーションのための道具箱であり、リノベーションのためのヒントや道具建てをたくさん用意している。HOUSE VISIONが考える「インフィルデパートメント構想」のもっとも基本的なカタチではないかとも思う。リノベーションはサブカルチュアから始まり、少しずつ社会に定着して、ついには無印良品も参画するようになって、産業の入り口まで来ているのが現状ではないだろうか。

- 大島芳彦 Yoshihiko Oshima
クリエイティブディレクター・株式会社ブルースタジオ 専務取締役 - 1970年東京生まれ。1993年武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。The Bartlett,University College London(英国)、Southern California Institute of Architecture(米国)に学ぶ。石本建築事務所を経て2000年にブルースタジオ取締役就任。2009年より一般社団法人リノベーション住宅推進協議会理事。建築家、不動産コンサルタントとして、自由かつ斬新な建築作品を多数手がける。特にコンバージョン・リノベーションにおいては、「ラティス青山」をはじめ、06年、07年にグッドデザイン賞連続受賞など高い実績を誇る。その他セミナー講演や執筆活動など、幅広いフィールドで活躍中。
物件から物語へ
ブルースタジオは社会的に一級建築士事務所という位置づけだが、宅地建物取引業でもあり、自己物件に関する不動産仲介も行っている。ブルースタジオがリノベーション事業を開始したのは2000年。先ほど馬場氏から話があった通り、この頃に時代の大きな変化を感じてリノベーションの仕事をスタートさせている。当時は「リノベーション」という明確な概念はなかったが、住宅の位置づけがこれから大きく変わっていくだろうと漠然と感じていた。それは生活者の価値観が大きく変わってきていたからだ。物質的に満たされていなくてもいい、という価値観の台頭だ。当時は、スッカラカンの空間の中で自己実現していく、キャンバスのような空間が何らかの価値を持ちうるのではないかと考えていた。
「物件」という言葉には常に引っかかっていた。私の祖父は土地開発を営む不動産事業者だった。父は貸ビル業、私自身は美術大学を卒業し建築設計の道に進んでいた。そのような環境の中で「物件」という言葉が頻繁に耳を通り抜けていく。物件とは何か。建築家が「作品」と表現する「物件」も、消費者にとっては「住まい」であり、不動産業者にとっては「商品」、金融機関は「担保」と捉える。それぞれが「物件価値」という言語を使うのだが、それぞれ別の方向を見ているという違和感は強く、大きな価値の損失を感じていた。。
衣食住の中で「住」は、衣食に比べて付加価値が産まれる環境が発達していない。これも「物件」に関与するプレーヤーがそれぞれ別の方向を向いているからではないだろうか。各者の視点が積極的に関与しあい同じ方向を向いて行くことが、付加価値の最大化につながる。異なる価値観、視点を融合する状況とは「物件」を一つの「物語」に昇華させるという認識で、私たちはまさにこの「物件から物語」のイメージを活動のテーマにしようと考えたのである。
ハードウエアから
ソフトウエアへ
私たちブルースタジオの業務は、コンテンツマネジメント、アセットマネジメント、リーシングマネジメントの3本柱。言い換えるならソフトウエアデザイン(企画、マーケティング)、ハードウエアデザイン(建築設計事務所)、システムデザイン(流通、管理)。この3つのデザインで建物価値の最大化を図っている。
この10年、消費者の価値観は大きく変わってきた。人との比較による相対的な価値観ではなく、自分らしさとは何かという絶対的な価値観へ。それはハードウエアからソフトウエアへという流れに近い。仕事柄よくリフォームとリノベーションはどう違うのかと聞かれるのだが、私はこう考えている。リフォームは「問題解決」の直接的手段。医学で言えば対処療法。一方、リノベーションは根本から問題を考え直すこと。例えば生活スタイルを変えるといった、問題の根源に立ち返って状況を変えていくことだ。医学で言えば原因療法。
ライフスタイルの変化
私たちにはB to BとB to Cの二つの仕事の軸がある。B to Cについては注文住宅の設計を不動産の取得からサポートする。住む場所を選ぶ、という行為が生活をデザインすることの第一歩と考えているからだ。特に土地ではなく、より選択肢が豊富な既存(中古)住宅を、都市で暮らす器として住みこなすことを提案している。B to Bに関しては収益性が低下した既存収益物件(賃貸住宅)を再生させるコンサルティングである。生活者から見れば借りる(貸す)と買うことのサポートを手がけていると言ってもいい。
この「借りると買う」という従来からの二元論的な概念の間に、この10年間でさらに二つの新しい住い方の選択肢が生まれてきたと私は考える。これを「新賃貸派」と「流動資産派」と呼んでいる。不動産資産の価値が下落し、世帯所得も低下する中、住むことを目的とした負債(住宅ローン)は生涯にわたって背負いたくないと考える人種が現れる。そこで積極的に賃貸住宅を臨機応変に住み替える生活を選択するのが新賃貸派。彼らにとって賃貸住宅は購入前の仮住まいではない。その瞬間において最善の自分らしさを住環境に求める。一方、流動資産派は生涯にわたって2度以上住宅を購入する人種。30代のうちは価格、広さ的にも身の丈サイズの中古住宅等を、近い将来貸す、売ることを前提に購入し、自分仕様にリノベーションして暮らす。
編集し直す
私の仕事は「編集」だと思っている。住いの価値を決める要素はさまざまだ。耐震強度や管理、立地、内装……。それらの要素には不動産業者、建築家など各業界にそれぞれが違う座標がある。しかし生活者にとっては全てが理想の住まいという観点において同じ座標の上にある問題だ。どうしても取り揃えたい家具のプライオリティーを重視し、駅からの距離を予定より多少遠く設定して物件の値段を下げこの夢のバランスをとる。不動産業者も想像しないような臨機応変な編集感覚が生活者にはあるのだ。例えば代官山や自由が丘に住みたいと語る人にとってそれは本当に重要な要素なのだろうか。これまでの不動産業者にはそれを冷静に助言できなかった。しかしどこよりも先に私たちのところに相談に来れば、全ての編集が可能だ。中古住宅を住まいの選択肢と考えれば、新築住宅の購入を検討する人とは比べ物にならないくらいの選択肢が現代の家余り社会ではみえてくる。それが中古住宅の魅力だ。
私たちは現在年間40~50件ほどの中古住宅購入の仲介+リノベーション設計を手掛け、これまでの実績は約320件に及ぶ。いわゆる「流動資産派」の彼らの傾向はグロス価格で4000万円前後、専有部広さで60㎡前後、都心立地である。しかし、この1年で90㎡オーバーのクラスも増加傾向である。この層は流動資産というよりも安定した固定資産の価値を重視し、古いけれど新築ではほぼ不可能なスーパープレミアムロケーションに位置するいわゆるビンテージマンションを安価に購入し、自分仕様のリノベーションを楽しんでいる。いずれも「新築購入」では決してできないことを、中古住宅というフィールドで自由にやっている。
編集し直新賃貸派と
コンバージョン

次にコンバージョンの事例を紹介したい。私たちが収益物件を棟単位で再生する場合はまず建物を見るのを止める。鳥瞰の視点で周辺環境がどう変化したのかを見るのだ。建物をまるごと再生させるということは、その街における建物の存在意義を問い直す必要があるからだ。青山一丁目駅真上にある某企業本社ビルとして使われていた延べ床面積約2,000平米のオフィスビル。1960年代の竣工当時から約40年以上某企業の本社ビルとして利用されてきたビルも、その企業が建物を明け渡した現在、一棟まるごと再度大企業のオフィスビルとして再生させることは経済合理性と競争力の点から不可能と考えられた。そこで私たちは街と建物の関係を再考した。
青山一丁目は周辺に都営住宅もあり、周辺の商業地域に比べると比較的賃貸住宅が安価なエリアでもある。地の利だけでなくそこに目を付けているクリエイティブな人々がこのエリアのマンションを借りてオフィスとして使っている。そうした人々にとってエリアのアイデンティティあるいは機能的ハブとなりうるような、能動的なものをつくろうと考えたところから、クリエーターズビレッジ構想が生まれた。住宅というよりは24時間使えるSOHO空間と考え、内部は非常にシンプルなスケルトンの部屋として2階以上に40ユニットを用意した。同時に路面には建物のシンボルでもあり彼らにとっては利便施設でもあるカフェを誘致した。カフェは午前3時までフードの提供をする。さらに輸入書の書店が出店し、地下の従前の機械室部分にはフォトスタジオが入居した。クリエーターズビレッジのコンセプトをベースとしたテナントミックスである。これは地域的なニーズを捉えた再編集と言えるだろう。こうしたコミュニティーとして明確なコンセプトをもつ物件にはある種のフィルタリング機能が働き、そこに集まってくる人々は皆同じ世界観を共有し、さらには利用者同士で新しい仕事が誘発されている。大きなプロモーションを行わなくても、建物にコンセプト、つまり明確な物語があるが故にユーザーの自発的な紹介で常に高稼働率を維持している。

東京の大田区では長屋を6棟所有するオーナーの事例も興味深い。品川から15分で太陽があり庭があり路地がある暮らしがある。品川のオフィスには働く感性が高い人々がいて、彼らにはスローライフが価値を持つ。そこで耐震改修しながら当時のライフスタイルを現在に継承することを考えた。路地的な人と人のつながりを付加価値として、庭も開放し、縁側を設ける。プライバシーを完全に確立させた問題解決型のリフォームで手掛けたなら、セキュリティは物質的なものに依存せざるを得なくなり、そうなると新築にはかなわない。
日本がかつて持っていたシンプリシティという考え方で再生させた例である。価値観を共有する人々が集まる中では仕掛けを行ったのは最初だけで、その後は住民が自発的にさまざまなアクティビティを生み出している。再生という手法によって理想的なコミュニティーが生まれたばかりでなく、コスト、リスクは最小限に押さえられ、効果的なキャッシュフローも生まれている。

- 長坂 常 Jo Nagasaka
建築家・有限会社スキーマ建築計画 主宰 - 1971年大阪府生まれ。1998年東京藝術大学美術学部建築学科卒業。スタジオスキーマ(現:スキーマ建築計画)開設。2007年事務所を上目黒に移転。ギャラリーなどを共有するコラボレーションオフィスHAPPAを設立。 主な受賞に2004年『Kitchen cafe Cube』JCDaward、2008年『sayama flat』bauhaus award2008 2nd Prize。主な作品に、2007年Sayama flat、2008年bench2、Flat Table、2009年HAPPA HOTEL、Aesop Aoyamaなど。2010年LLOVE展参加。主な著書『B面がA面にかわるとき』(株式会社大和プレス/2009年) 2011年ミラノサローネでSpazio Rosana OrlandiにFlatTable_peeled出展予定、LIVING@LOUISIANA museum of modern artに出展予定。
Space for Imagination
私の仕事の三本柱は、建築、インテリア、家具のデザインだ。もしデザインの辞書が世界共通であるとするなら、その1ページを書き換えることがデザインの仕事ではないかと思いながら仕事をしてきた。最近、リノベーションをやりながらテーマとしているのは「Space for Imagination」。これは想像可能な場所をつくる空間創造の方法。先にお二人が話していた何かに参加していくような自発的な場所を指しているとも言える。それに気づくきっかけとなったのは、ギャラリスト、デザイングッズ販売と私たちの事務所など4者で共有しているシェアスペース「happa 」だった。実際に自分たちがこのスペースに参加して、変えていく喜びをもって「Space for Imagination」に気づいたのである。
「Space for Imagination」は私の中では一人称で物事を伝えることではなく、情報の隙間ができるような空間だ。簡単に説明すると、二人で話の溝が埋まらない場合は三人目が必要になる。そういう空間のつくり方が必要なのではないかと考えている。リノベーションはその点においても優れていると思う。なぜなら最初から客体が存在していて、そこに自分の存在を重ねた時に必ず生じるズレの部分が「Space for Imagination」であり、その取扱をどうデザインするかを考えることができるからだ。これから紹介するものはリノベーションの中でどうやって新築に負けないものをつくろうかとか、見えている風景をすべて刷新する考えの下でデザインしたものだが、どうしてもほころびが見えてくる。そのほころびをどうするか。具体的には手を付けられない共用部が風景として見えてくる。江戸川台にある住居兼医院を教会にコンバージョンした「江戸川台教会」(2006年)の頃から、既存のものを受け入れていくしかないと考えるようになった。
足すのではなく引く
「Sayama flat」(2008年)は、圧倒的に転換されたプロジェクトだ。郊外にあり築30年以上で不動産としては扱いづらい物件だった。社宅で利用していた30室が突如空室になった。その30部屋を何とかしなければならない。立地上、予算はかけられない。一部屋100万円で何とかならないかという設計依頼だった。私は、自分の部屋に100万円使えるならそれなりに見せられるものはできるという、安直な発想でこの仕事を請けてしまった。
結果的に私が行ったことは「足すのではなく引く」。そして文脈を書き換える。夏目漱石の「吾輩は猫である」の冒頭、「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」の既存の文章から言葉を引くと「吾輩は名前は無い。」という新たな文脈をつくることができる。これと同じことがリノベーションでもできるのではないか。例えば、壁があることで関係性がなかった洋室と和室を、壁を取り去ることでいきなり隣接させる、など。このプロジェクトで自分は何もつくっていない。壁を抜いただけだ。光を求めて壁を取り払い、その結果出てきた構成に対して文脈をつけてあげるため少しだけ整理した。最初は「こんな襖なんて」とか「こんなキッチンなんて」と思えていたものが、この経緯を踏んだことで「いいじゃん」と思えることが、自分の体験の中でできた。この体験はとても刺激的で、まちの風景すら、何か足したりつくりかえたりしなくても変わる可能性があると考えるようになった。
東京に大量に
残っているものと
どう向き合うか
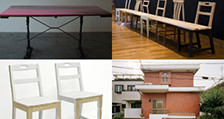
これ(※写真左上)はアンティークのテーブルの上に着色したエポキシを流し、フラットにすることで色の濃淡が海のように浮かび上がる。アンフラットなものをフラットにすることで、アンフラットな模様が生まれる。どこにでもある椅子を寄せ集めてベンチをつくる(※写真右上)。座面から上だけを研磨する。これだけで捨てられていたような家具が再生する(※写真左下)。十分な強度がある木製の椅子のフレームをカットして減らしていくことで、違う椅子をつくる。それから半年経って、手掛けたプロジェクトが「奥沢の家」(※写真右下)。私はリノベーション前の、この少しお金持ち風の昭和の家を「スネオの家」と呼んでいたのだが、今の時代においてはカッコ良いとは思えない。だけど無視はできない。戦後を経験した人々の当時特有の憧れのカタチで、こうした家は東京に大量に残っている。この家とどう向きあっていくか。これにツッコミを入れるように手を入れることはできないか。そのために過去を否定するでも、肯定するでもなく、既存の仕上げも、新たに加える仕上げも等価に扱い、それぞれの意味の反転と体験における内外の反転を試みた。周辺の住民は確実にかわったことはわかるが、何がどうかわったか限定しづらい無意識の隙間に入りこむ変化を試みている。

「Aesop」のショップ(※写真左)は、スケルトンのスペースに、偶然見つけた取り壊し寸前の木造住宅の材料をメインにつくりあげたデザインである。スケルトンには一切手を入れず、外壁がサッシの内側になったり、コンクリートを剥がした土もそのままに、偶然見つけた古材を什器の縦方向に使い完成した空間だ。昨年のデザインタイドの一環として行われた代官山の「LLOVE」(※写真右)では、プロジェクト終了後、建物に囲われている庭の部分を開く提案を行っており、それが実現できるだけで、この建物は再生できるので
終わりに|原研哉
私たちは住宅に対するリテラシーは誰からも教わらない。日本の住まい方はこの50年で激変してしまったが、そろそろ教養としてリテラシーを持とうという機運は感じられた。さらにリノベーションの土台であるスケルトンに関しては、認識も評価軸も法も不足している。ここに多くの人々の知恵を集結して解決することは大きな成果を生むのではないかと感じた。震災と原発事故は日本に甚大な被害をもたらしたが、視点を変えれば日本が環境先進国になるチャンスであり、その動きが加速していくだろう。今、夜の都市は暗いけれど、この暗さが心地よい。都市は光でデザインされるのではなく闇でデザインすべきだったと、多くの人々が気づき始めている。これらも意識しながら今後議論を進めていきたいと思う。
文責=紫牟田伸子