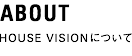最初の展覧会を終えて
 最初の展覧会が終わった。オープン直後のひと時、春一番の強風に悩まされたこともあったが、23日間の会期中、開会中に雨の落ちたのは僅か1時間のみ。奇跡的に天候には恵まれた。今年は例年より10日ほど早い桜の開花だったが、その分HOUSE VISIONの会場もうららかな陽光に恵まれての開催となった。交通不便なお台場の、耳慣れない「青海」という空地に会場をしつらえ、入場料を設定してという、集客には厳しい諸条件だったが、facebookやtwitterなどのSNSの情報拡散を背景に、最終日にはチケット売り場に長い行列ができた。23日間の会期で3万4千人。日を追って入場者数が跳ね上がっていく来場傾向には少なからず高揚感を覚えた。来場者はとても若く、最も多かったのはデザイン・建築系の学生だったが、会場では至る所に乳母車を押す家族の姿や、走り回る小さな子供の姿があった。書籍『HOUSE VISION 2013 TOKYO EXHIBITION』は会場だけで2000冊を越える記録的な販売実績となり、全国書店での販売も3月22日より始まっている。
最初の展覧会が終わった。オープン直後のひと時、春一番の強風に悩まされたこともあったが、23日間の会期中、開会中に雨の落ちたのは僅か1時間のみ。奇跡的に天候には恵まれた。今年は例年より10日ほど早い桜の開花だったが、その分HOUSE VISIONの会場もうららかな陽光に恵まれての開催となった。交通不便なお台場の、耳慣れない「青海」という空地に会場をしつらえ、入場料を設定してという、集客には厳しい諸条件だったが、facebookやtwitterなどのSNSの情報拡散を背景に、最終日にはチケット売り場に長い行列ができた。23日間の会期で3万4千人。日を追って入場者数が跳ね上がっていく来場傾向には少なからず高揚感を覚えた。来場者はとても若く、最も多かったのはデザイン・建築系の学生だったが、会場では至る所に乳母車を押す家族の姿や、走り回る小さな子供の姿があった。書籍『HOUSE VISION 2013 TOKYO EXHIBITION』は会場だけで2000冊を越える記録的な販売実績となり、全国書店での販売も3月22日より始まっている。
毎日開催されたトークショーは、いずれの回も満席に立見の出る賑わいを見せ、参加いただいたスピーカーの幅広い顔ぶれを通して、同企画の趣旨を多角的に社会に発信できたことを実感している。40を数える建築家や諸分野の専門家の方々、参加企業の代表の方々とのセッションを通して、日本の現状と未来をリアルに学ぶことができた。
この企画をもう少し早くからやるべきであったという内藤廣氏の批評は、GOOD DESIGN AWARDの審査委員長として、日本の工業製品の行き詰まりを切実に感じられてきた経験を踏まえての発言で、企画者としては我が意を得た思いであった。一方、建築系の批評筋からは、「家」の建築的な未来性をどう捉えているのかという厳しい意見も、ネット上のつぶやきに散見した。ある意味では予測通りの反応。あえて従来の建築文脈の批評を越えて、社会や素人、企業や生活者を巻き込んだ「家」への興味の喚起と、産業連繋への視点、そして時代を牽引する消費の傾向を生み出していくことを目的としており、批評は批評として、避けず受けとめたいと考えている。奇しくも、対岸の汐留で、二川幸夫「日本の民家 一九五五」展が開催されていたことも、よい批評となった。かつて確かにあった日本の暮しの風景は、現代に生きる僕らの喉元に、鋭い問いを突きつけてくる。それだけに、かつてあった風景を、ただ美しいと評する無責任を乗り越えて、僕らが歩を進める意味がそこに見いだされる思いがした。
VISIONとは「未来をそれと見定める」ということである。2050年あたりを見定めつつ、縮退していく日本を上手に畳みながら、経済活動のフィールドはアジア全体に拡張して、産業の広がりを見立てていかなくてはならない。そのためには住宅は、建築的批評の土俵から外へ踏み出して、一般生活者の「家をつくろう」という能動性をいかに引き出せるか、あるいは、アジア全体への産業的拡張を、総合的製品としての住宅を基軸に、どう誘発できるかという視点から捉え直されなくてはならない。
参加企業の代表の方々にはそろって会場に足をお運びいただくことができた。同企画の趣旨を、具体化された会場と展示ハウス、そして来場者の反応を通してご理解いただけたと確信している。
また、中国やインドネシア、台湾、シンガポール、カンボジアなどアジア諸国からも見学者は訪れ、特に中国の不動産大手2社の経営トップも欧米の出張先や留学先からわざわざ来場された。どうやら展覧会の終了にのんびりとはしていられないようだ。
HOUSE VISIONは第一回目の成果を踏まえ、さらに実践的視点から研究と活動を続けていきたいと考えている。今後は、興味を示していただいたより多くの企業と連繋し、三年に一度のトリエンナーレとしての開催を構想しつつ、まずは研究活動へと活動形態を戻したい。